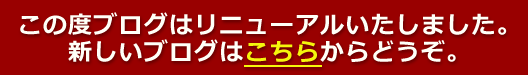���������륳�륿��Ȥ����ߥʡ����ʾ塢�Ⱥ߸ˤϺ�ǤϤʤ��ɤȤ���ȯ����
��פ�ؤ����Τ��餹��С������ְ�ä����Ǥ���ޤ���
���Υ��륿��Ȥ��������������Ȥ��������θ��դβ��⤬��Ƥ��ޤ�����
ê���κ߸ˤϲ�������Ȼɤ˷夵����Τ������Ȥ��ƤΡȲ��ͤ��㤤�ɤȤ����Τ�����ȯ���μ�ݡ�
�߸ˤ����äϡ����ж⎣�ǻ�ⷫ��ΰ����ˤĤʤ���櫓�Ǥ���ޤ���
�����ơ��߸ˤ�¿���ʤ�Ȏ����ɺ߸ˎ�������Ū�����ä���Ȥ�����Ρ�
���Υ��륿��Ȥϡ����ιֱ����ǡ����߸ˤ����Ĥ꾦�ʤʤΤ����顢���κ߸ˤ�Ȥ��Ʒ夹��ΤϤ�äƤΤۤ�����줿���ʤ���������ǤϤʤ��������줿���ʤϤ��Ȥ����ĤäƤ����Τ����äƤ⤹�٤Ƥ����Ȥ���ª����٤��������Ȥ⡣
�ʤ�ۤɡ���äȤ���äǤ���ޤ���
������ۡ��ᡡ���۷��� ���Ȥ���С����ޤ��ˡ����סɤȡȥ���å���ե����ɤϡ�ɬ�����פ���Ȥ�����ΤǤ���ޤ���
���ޤǰʾ�Υ���å���ե����бĤμ����������¸³�θ��Ǥ���ޤ���
»���̤����ǤϤʤ�������å���ե����ޤǰʾ�˰ռ������бĤҿ������ޤ��礦��
�Ȥ�����̣�ǡ�����̳��Ǥϡ��������(��)�θ�壱����ꡢ�ػ�ⷫ��˻������֤������褢��٤��бĤ�ͤ��륻�ߥʡ��٤Ť����Ƥ����������ȤȤʤ�ޤ�����
����ϡ��ʤ�ȡ���ͻģ���ô�����ˤ�����ĺ�������澮��Ȥλ��Ĵã����Ω�Ķ�ͻ�������μ����ˤĤ��Ƥ��ä�ĺ���뤳�ȤȤʤ�ޤ�����
��¿�ˤʤ�����Ǥ���ޤ���
���������Ϥɤ�����������ͻ���Ƚ��Ƥ���Τ��������κ���δ�ȷбĤ�ɬ������Ω�����ƤǤ���ޤ���
�������̵���ǡ��ɤʤ��Ǥ��硦�紿�ޤǤ���ޤ���
�ܤ������Ƥϡ��������ɥ쥹��å����Ƥ���������
http://www.yamanobo-zeirishi.jp/new/
�������¤ϣ�������ǡ�����ϣ���̾�Ǥ���
�����Τ��������ߤ�����
�ä��Ѥ��ޤ���
����ͼ���������ΰ��ܤ����ä���������
�������黲�ı��Ρ������Ρ����ȿ����ޤ����¤ϡ���������ΡȽ�Ĺ�ΤҤȤꤴ�ȡɤˡ���ͻ���륿��Ȥ���¼���Ρ��澮��Ȥμ�������ֺѤ��Ĺ��ǯ�����ɤȤ�����Ƥ�Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ��������ν�ŵ�Ϥɤ��Ǥ��礦�����Ȥ����䤤��碌��
�ԣˣò���˷Ǻܤ��줿�����ʤΤǤ���������椫�꤫�Ǥʤ��ä��Τǡ������ֹ��ʹ������Ĵ�٤���ˤ�Ϣ�������Ƥ������������ݤ��������Ȥꤢ�������ä����ǡ�
��ʬ�塢����Σ����Ǥ�������ä��Ƥ����������Ȥ����Ǥ���ޤ���
�����Ź��ͻ��������ô������澮�����ٴ�Ȥؤζ�ͻ����ͻ��佻���������ֺѤ�ǯ����ͱͽ�������֤�Ȥ�٤����Ȥ���ȯ��������ƤΤ���ͤ�ư���Τ褦�Ǥ���ޤ���
����ˤ��Ƥ�Ӥä���Ǥ���ޤ�����
��ιԤ�ƻ�����Ȥ��ƻ٤��Ƥ��뤪��ͤ������֥������ɤޤ�����ä��Ƥ�����Ȥϡ�������
��®���λݡ���¼��������Ϣ����������Ǥ���ޤ���
��ī�ο�ʹ�ˤ��ȡ������Ź���äϡ��������Ƥ��٤���������Ƥ���ȤΤ��ȡ�
����ȯ����;�Ȥ�����ơ������γ����Զ��ϡ����
�äˡ��澮�����ٴ�Ȥ�ܵҴ��פȤ���������Ԥ��礭������ȤΤ��ȤǤ���ޤ���
���ҡ�������ǡ�����ι��������ܤ����Ȥ����Ǥ���ޤ���
�����Τ���������⡢�������ʥơ��ޤǤ��룱������Υ��ߥʡ��ˤҤȤ�Ǥ�¿�����������黲�ä�����������ȻפäƤ���ޤ�����������
����ȯɽ���줿������ϲ���
���㸩�ϣ�ǯ�֤�β���Ψ�γ���(��������β���)�Ǥ���ޤ���
�����������֥��������ߤˤʤ�ޤ��Τǡ������Ϥ�����������
��֥�����˻��ä��Ƥ��ޡ��������٥��ȣ���̴�ǤϤ���ޤ����ҡ����Ҽ����ФΥޡ�������������å��Ƥ����������鹬���Ǥ�������

![]()